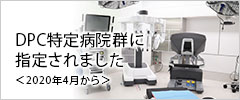消化器内科
当科では、上下部消化管および肝胆膵疾患に関する内科診療を幅広く行っています。従来から消化器領域の救急疾患(消化管出血、閉塞性胆管炎、重症急性膵炎、劇症肝炎、腸閉塞など)の診療体制を充実させて近隣の医療機関からの紹介を数多く受け入れており、北和医療圏の中核的役割を担っています。医学的に高度な集中治療を必要とする重症例に関しては、併設の救命救急センターと緊密に連携しています。また、地域医療連携は特に重視しており、かかりつけ医の先生方と緊密に連携して日常診療にあたるよう努めております。
診療内容
上部消化管(食道、胃、十二指腸)、下部消化管(小腸、大腸)、肝胆膵の消化器疾患全般にわたり、専門的な診療技術を提供しています。
1.消化管
消化器内視鏡診療においては、最新の医療機器を駆使して消化器内視鏡専門医が外科医と連携しながら、腫瘍性疾患や緊急疾患の検査や治療に携わっています。また、国内外で急激に患者数が増加している炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病など)の患者さんを積極的に受け入れており、日本炎症性腸疾患学会の指導施設にも新たに認定されています。
- 画像強調や拡大観察による上下部消化管疾患(潰瘍、ポリープ、がんなど)の詳細な内視鏡診断および早期の食道がん・胃がん・大腸がん等に対する内視鏡的治療(内視鏡的粘膜下層剥離術ESDおよび内視鏡的粘膜切除術EMRは治療ガイドラインを尊重して安全かつ確実に実施)
- 消化管出血(出血性潰瘍、食道胃静脈瘤破裂など)に対する内視鏡的止血、義歯などの異物誤飲に対する内視鏡的異物除去術
- 各種生物学的製剤や免疫抑制剤等による炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病など)の最新治療
- カプセル内視鏡やバルーン内視鏡による小腸病変の診断と治療
- 超音波内視鏡検査による粘膜腫瘍の的確な深達度診断と、超音波内視鏡検査下穿刺吸引法(EUS-FNA)を用いた粘膜下腫瘍の質的診断
- 内視鏡的胃瘻造設(PEG)
2.肝疾患
肝疾患については、中核専門医療機関に指定され、肝がん診療拠点病院であるとともに、難治性肝疾患やウィルス性肝炎などの幅広い肝疾患診療を行っています。近年、慢性肝疾患と糖代謝異常をはじめとした生活習慣病が密接に関連していることが報告されており、当科から独立した糖尿病・内分泌内科とも密接に連携しながら診療しています。また、最近では分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬の登場によって進行肝がんに対する治療法も大きく変化しており、症例毎に最適な治療法を提案できるように心懸けています。
- 症例毎に最適な肝がん治療法を選択(最新治療アルゴリズムに基づき、腫瘍の大きさや部位、個数などを考慮して症例毎に最適な治療法を決定。例えば、限局病変にはラジオ波焼灼療法(RFA)やマイクロ波焼灼療法(MWA)、複数個の病変には肝動脈化学塞栓療法(TACE)、進行例には分子標的薬などを選択。)
- 肝硬変合併症(腹水、食道胃静脈瘤、肝性脳症など)に対する集学的治療
- 直接作用型抗ウィルス剤や核酸アナログ製剤などを用いたウィルス性肝炎治療(非代償性C型肝硬変に対しても、現時点で肝がんがなければ実施可能)
- 難治性肝疾患(自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎、原発性硬化性胆管炎など)や代謝異常関連脂肪性肝疾患/代謝異常関連脂肪肝炎(MASLD/MASH)についても専門的な診療を実施
3.膵・胆道疾患
膵・胆道疾患に対しては、最新の内視鏡機器を積極的に用いて、的確な診断と治療を行います。
膵・胆道がんの早期発見・早期診断を目指し、超音波内視鏡下の組織採取(EUS-TA)などによる病理組織学的診断や、スパイグラス(*当科HP『治療について』を参照)を導入し、膵胆管の内部を直視下に観察しながら、膵・胆道疾患の精度の高い画像及び内視鏡診断に努め,消化器外科と連携し、集学的治療を行っています。また,小腸内視鏡(*同)を用いた術後再建腸管に対するERCP関連手技や、超音波内視鏡(EUS)を用いた経消化管的な胆道ドレナージや膵嚢胞・膵管ドレナージ,難治性総胆管結石に対するスパイグラスを用いた結石除去,乳頭部腫瘍に対する内視鏡的乳頭切除術など、最新の内視鏡治療にも積極的に取り組んでいます。
- 内視鏡的膵胆道造影(ERCP)を用いた検査・治療(小腸内視鏡を使用することで消化管手術後の症例にも対応)
- 内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST)や内視鏡的乳頭バルーン拡張術(EPBD)による総胆管結石治療(スパイグラスを用いた電気水圧衝撃波により難治性総胆管結石にも対応)
- 閉塞性黄疸に対する内視鏡的胆道ドレナージ術
- 超音波内視鏡下の組織採取法(EUS-TA)を用いた膵腫瘍性病変の診断
- 超音波内視鏡下を用いた経消化管的胆道ドレナージ,膵管ドレナージ
- 仮性嚢胞に対する膵嚢胞ドレナージ,内視鏡的壊死組織除去術など
4.各種消化器がん
当院は「地域がん診療連携拠点病院」に指定されており、当科では主に消化管領域(食道、胃、大腸)のがんや肝胆膵領域(肝臓、胆管、胆嚢、膵臓)のがんに対して、以下のような内科的がん治療に取り組んでいます。
- がんの診断および最適な治療法の決定
- 切除不能進行・再発がんに対する化学療法
- 院内各診療科との連携や紹介
- 緩和/支持療法
- 近隣医療機関との連携や紹介
なお、各学会が発行する診療ガイドラインや新しい科学的根拠などに基づいた治療提案(EBM:Evidence Based Medicine)を基本としていますが、毎週開催する消化器内科・消化器外科・放射線科の合同カンファレンスで各領域の専門医が協議して、それぞれの患者さんにとって最適な治療になるようにも努めています。その他、集学的がん治療センター、腫瘍内科、緩和ケア内科などを中心に院内の各診療科とも幅広く連携しながら、消化器がんの治療に取り組んでいます。(詳細は当院の集学的がん治療センターのホームページをご参照ください。)
また、近年では従来の抗がん剤に加え、分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬が使用可能になり、治療選択の幅が広がりました。これらの新規薬剤は従来の抗がん剤よりも治療効果が期待できる可能性がある反面、重篤な副作用を生じることがあります。そのため、他の診療科との連携をより深めながら診療をしています。
特に、肝臓がんに対しては化学療法を継続するだけではなく、治療反応性を評価しながらカテーテル治療(IVR)や外科手術、放射線治療などを組み合わせた集学的治療により、進行期の患者さんに対しても予後の改善を目指して積極的に取り組んでいます。
その他、胆膵がんなどの治療中には、胆道ステント留置術や消化管ステント留置術といった内視鏡治療が欠かせない状況に陥ることもありますが、それらの場合にも適切に内視鏡治療を行うことで、抗がん治療の長期継続の実現を目指します。
■がん告知に関して~検査や治療に支障をきたさないために~
がん診療に際しては、患者さん本人に病名告知が正しく行われない場合、検査や治療に支障が生じる場合があります。そのため当科ではがん診療に際しても、原則として患者さん本人に病名を明確にお伝え致しますので、予めご了承ください。
なお、本件に関してご家族からの相談希望などがございましたら、事前に看護スタッフ等を通じて外来担当医へご連絡ください。
外来担当表
|
月曜日 |
火曜日 |
水曜日 |
木曜日 |
金曜日 |
| 1診 |
松尾(英)(消化管) |
久保(消化器) |
守屋(消化器)【午前】
守屋(IBD)【午後】 |
中西(消化器) |
永松(肝胆膵)【午前】 |
| 2診 |
守屋(IBD)【午前】 |
森本(消化器)【午前】
川﨑(消化器)【午後】 |
菊川(消化器) |
藤本(消化器) |
松尾(悠)(消化器) |
| 3診 |
友岡(消化器) |
|
永松(胆膵)【午前】
松尾(英)(消化菅)【午後】 |
|
|
外来受付:午前8時30分~午前11時00分まで(予約、急患を除く)
セミナーのお知らせ
【医療従事者向け】「IBD診療における多職種チーム」
臨床研究と治験の紹介
当科では、われわれが診療を担当する疾患の医学的な診療力向上を目指しています。それに伴い、各種の多施設共同臨床研究や新薬開発に関わる臨床治験にも積極的に関わっています。詳しくは、担当医あるいは診療部長にお尋ね下さい。
大腸がん検診後の二次精査で下部消化管内視鏡検査を希望される患者さんへ
当センターでは、下部消化管内視鏡検査の依頼件数が実施可能件数を大幅に超える状況が長らく続いております。そのため、検査数を可能な限り増加させるべく、これまで院内で様々な取り組みを重ねて参りましたが、検査依頼数の増加は著しく、これらの課題を解決するには至っておりません。そのため、早期に内視鏡治療が必要な症例の待機期間が長期化している現実も生じています。
このような状況を鑑みまして、2023年以降、当センターでは大腸がん検診の2次精査で実施するスクリーニング目的の下部消化管内視鏡検査の受託を辞退させて頂くことに致しました。
皆様にはご不便をおかけ致しますが、何卒、ご理解とご協力を賜れますようによろしくお願い申し上げます。
奈良県総合医療センター
消化器内科 部長 守屋 圭
内視鏡部 部長 松尾 英城